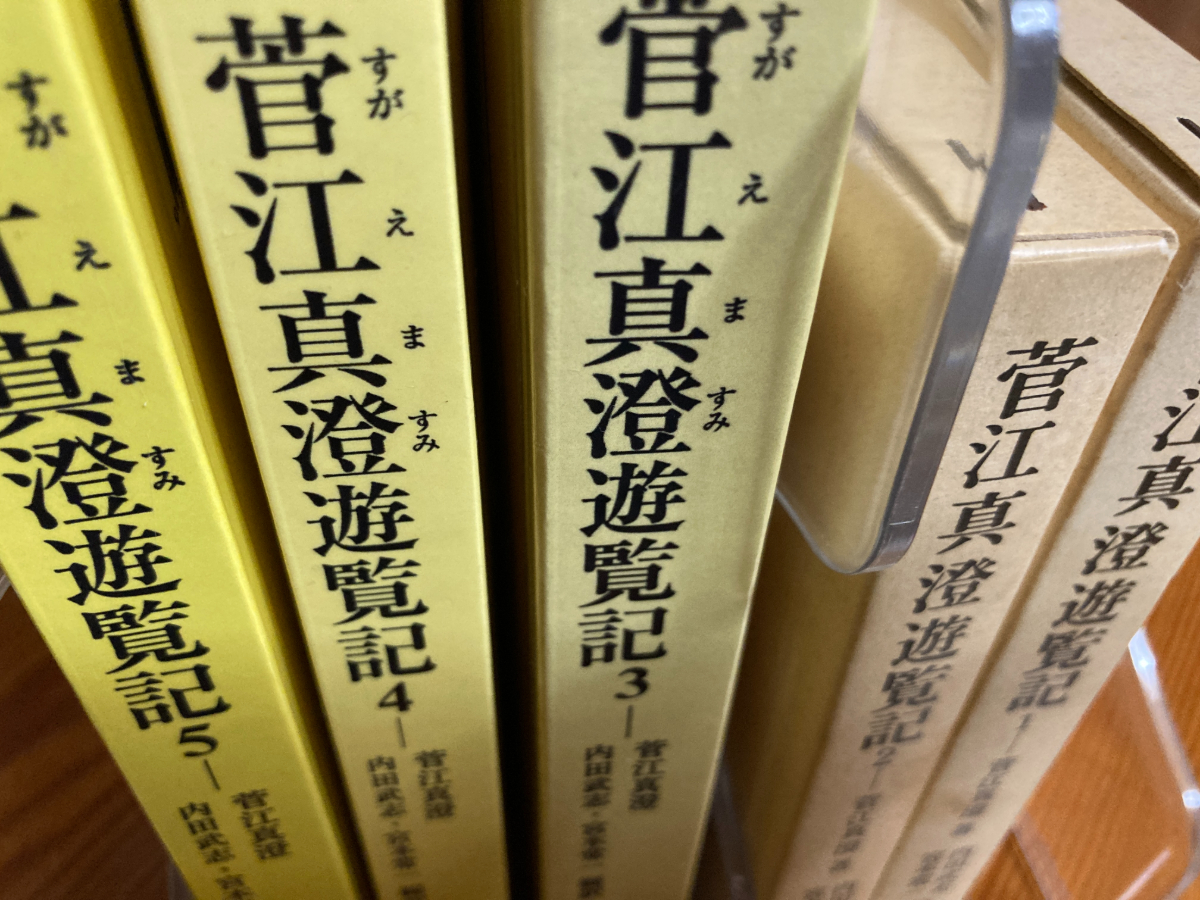津軽のをちについて
江戸時代の紀行家菅江真澄の「津軽のをち」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政9年(1797)の旅です。
菅江真澄は深浦に滞在しています。弘前に行きますが、体調が悪くなって寝込んでしまいます。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政9年1月1日は新暦では1月28日にあたります。日記が終わる6月1日は6月25日にあたります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「津軽のをち」からの引用です。
寛政9年1月1日
深浦に滞在しています。津軽の遠地(をち)、ここでは深浦のことです、にとどまって2年になり、3年目の元日だと書いています。
とし男をつとめる主人はそっと起き出して、ゆずり葉をさした提桶(さげおけ)で花(若水のこと)をくみます。
提灯をともして、うちとの神(神明)に詣でます。菅大臣をまつる祠(天神)などにも詣でます。雪がふりつもっている神社は離れたところから拝みます。停泊していた筑紫の船で乗初めの祝をしています。
1月2日
深浦に滞在しています。年始の挨拶をする子供たちに、「さあ、うまこにのせよう」と言って五葉松の小枝に一文銭をさして与えてます。これを銭馬と言っています。
1月3日
深浦に滞在しています。雪が降り続いています。
1月7日
深浦に滞在しています。ここでは七草は行いません。
1月8日
深浦に滞在しています。女たちが大ぜい海辺で紫菜(のり)を摘んでいます。
1月11日
深浦に滞在しています。竹越の家で船魂の祭があり酒宴が行われます。
1月14日
深浦に滞在しています。
囲炉裏の灰をならした後に火ばしで灰をついてはいけません(鴨が苗代を荒らす)。餅と魚のひれをさした長串を戸口や窓にさしはさむます。福鶴子餅というものを梁の上にあげたりします。十五日に、あかかゆ(小豆粥)、十六日に、しらかゆ(白米の粥)を食べます。などと深浦の風習について書いています。
1月21日
深浦に滞在しています。娘たちが集まって酒、肴で歌をうたっています。「びんちょ」といいます。男たちは「めだしの祝」をしています。
2月20日
深浦に滞在しています。彼岸には仏前に毎日餅を供え、人を集めて「茶のみ」ということをする。という深浦の風習について書いています。
3月16日
深浦に滞在しています。今日は鋤おろしの祝です。田の仕事をはじめる日です。
3月20日
深浦に滞在しています。うぐいすが初めてさえずり、つばめが来たと書いています。
4月1日
深浦に滞在しています。小島が遠くみえます。
4月8日
深浦に滞在しています。人形をたくさん小舟にのせて、笛太鼓ではやし、神主や大ぜいの人が従ってねりあるき、さいごに海に流します。「鹿島人形」といいます。
4月10日
深浦に滞在しています。停泊していた百隻以上の大船が、みな順風をえて出帆しました。
4月28日
吾妻の森、六所明神、あずまの浜を歩きます。
5月1日
深浦に滞在しています。「厚意に甘えて、もう一日もういちにちと出発をのばしていたが」五月になってしまったので出発しようと思いましたが強い雨ででかけられません。
5月5日
深浦に滞在しています。「やがて風がたってこよう。きょうの節句はここでしていきなさい」とすすめられます。
5月7日
深浦を出立します。「朝夕訪いあってしたしく語った友だちや、宿の主人をはじめ、みなが見送りをしようといって、幼い子供たちまでが自分の家の門口に立って、あるものは手をあげて、遠くなるまで手を振りながら叫んでいた。」
吾妻坂で送ってくれた人々と別れます。行合の坂、風合瀬、宮地、下村、館村、野中を経て、晴山が近づいたところで弁当を食べます。
関村を経て、かめ杉・阿弥陀杉を見ます。日が高いうちに鰺ヶ沢に着いて、七ツ石の雀部(さきべ)という酒屋に宿をとります。
5月10日
岡にのぼって眺望を楽しみ、昼から出立します。
立石村を経て、十腰内(とこしない)で雨になりそうだったので去年休憩した家に宿をとります。
岩鬼山大権現、十面沢(とつらざわ)、藤井、高杉、中別所、新岡村、高岡を経て、百沢に入り斎藤規房の家を訪ねます。
5月14日
百沢を出立します。一本柳、坂本、国吉村、黒土、清水観音、福村、中野を経て、中畑の村長三上某の家に宿を借ります。
5月15日
世の中の滝をみて、村市に入り去年泊まった家を訪ねます。
5月16日
平沢村、天狗森、沢田、小倉の神明社、岩屋の不動尊、追付、山田、前相馬、まそまへ、水木在家、紙漉沢、五所に入り、さらに如来瀬村に行きます。如来瀬村で泊まります。
5月17日
鳥野(鳥井野)、竜の口を経て、からない坂の眺望を楽しみます。弘前に入って、中井の家に入ります。
5月18日
医師小山内元貞の案内で、塩分町、白藤明神を経て、外瀬(とのせ)の藩主の薬園に着きます。藩医の会合に出席します。
5月24日
昼寝をしているときに間山祐真が訪ねてきてそのまま帰ってしまいます。
5月25日
和徳に間山を訪ねます。
5月26日
間山の家を出て、寺内、福田、外崎村を経て渡し船に乗って藤崎に着きます。去年泊まった川越某の家に泊まります。
5月27日
川崎の案内で旧跡をみてまわります。藤崎の城、稲荷の社、源九郎判官の馬を埋めたところ、唐糸の塚、福田の神、多門天王の堂を巡ります。
夕方、水木村に入り、毛利の家を訪れます。
6月1日
昼ころ夕顔堰の金医師の家に行きます。
熱が出て体調が悪くなります。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ