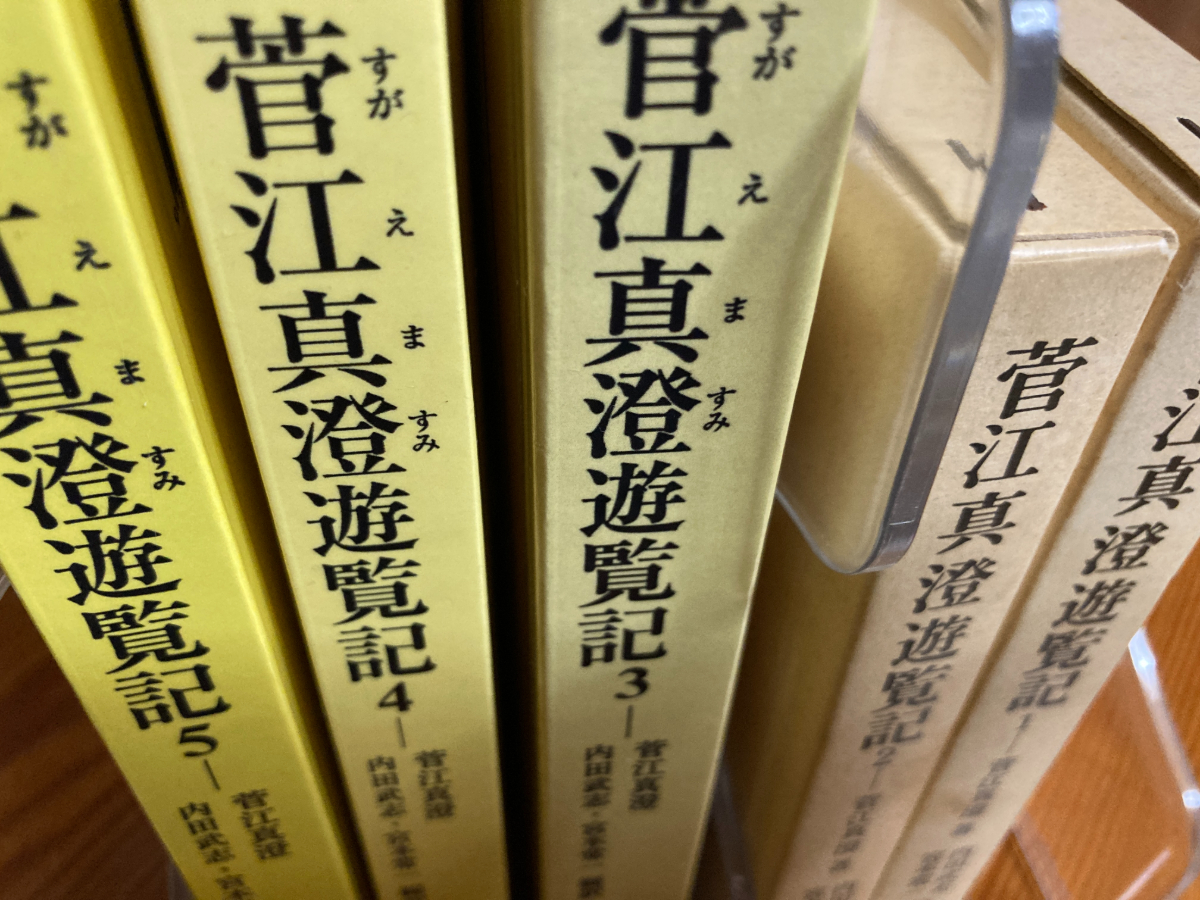雪の道奥雪の出羽路について
江戸時代の紀行家菅江真澄の「雪の道奥雪の出羽路」に出てくる通過地や滞在地をだどります。享和元年(1801)の旅です。
この少し前の寛政十一(1799)年の秋頃、真澄は藩庁(弘前)に呼び出され、取り調べの必要があるとして日記の大半を没収されてしまいます。このことが津軽を去ることにした理由だと考えられています。
菅江真澄は、滞在していた津軽の深浦を出立して秋田を目指します。ここでは秋田県内の部分は省略して津軽を出るまでの道筋を紹介します。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる享和元年11月4日は新暦では12月9日にあたります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記4「雪の道奥雪の出羽路」からの引用です。
11月4日
深浦に滞在しています。
秋ごろから出立しようと思っていましたが、日数をかさねているうちに雪の季節になってしまいます。11月3日に出かけよう決めていましたが、友人たちが送別の宴を開いてくれたので出立が一日延びます。
朝早く、旅装の用意をととのえると見送りの人びとから名残の歌を贈られその返歌をよみます。
出発し、浜辺にたたずんで遠方にみえる内外の社(神明)を遥拝します。木花開耶比売(このはなさくやひめ)の社のほとりで、「老若男女六十人あまりのひとびとが近づいてきて、くちぐちに挨拶した。」「また、こちらにおいでください。わるいものを食べてはいけません。馬から落ちないようにしてください。寒さに気をつけてごぶじに暮らしなさい。わたしは小石を拾って朝夕ごとにきよめましょう。これでお別れです」「わたくしの袖をひき、馬の鞍をおさえて、たくさんの人々が名残を惜しみ、とりどりにことばをかけてくれるので、ますます別れて行く気にならなかった」
竹越自養、宿の主人竹越貞易、大工の与之助が同行してくれます。自養は少し先で帰ります。与之助は最初の泊まるところまで見送って帰ります。貞易は藩境を一緒に越えて、能代を経て土崎まで同行してくれます。
深浦では船問屋を営む竹越里圭と深く交流しました。里圭は名主年寄役をつとめ俳諧の道でも知られた人でした。秋田の土崎まで真澄につきそってくれた竹越貞易は里圭の一族で真澄が滞在中の宿を提供していました。
めくら坂、金神の坂、岩崎を経て、沙間で萱森佐兵衛という知り合いの漁師の家に宿泊します。
11月5日
沙間を出立します。浜中、笹内川、久田、正道尻、森山、弓弦前(ゆづるまえ)川、松神村を経て、津梅(つばい)川の橋を渡り、大間越村で知り合いの菊池某の家で休息します。
関所を越え、境明神の祠を過ぎて出羽(秋田)に入ります。
再び津軽に戻ることはありませんでした。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ