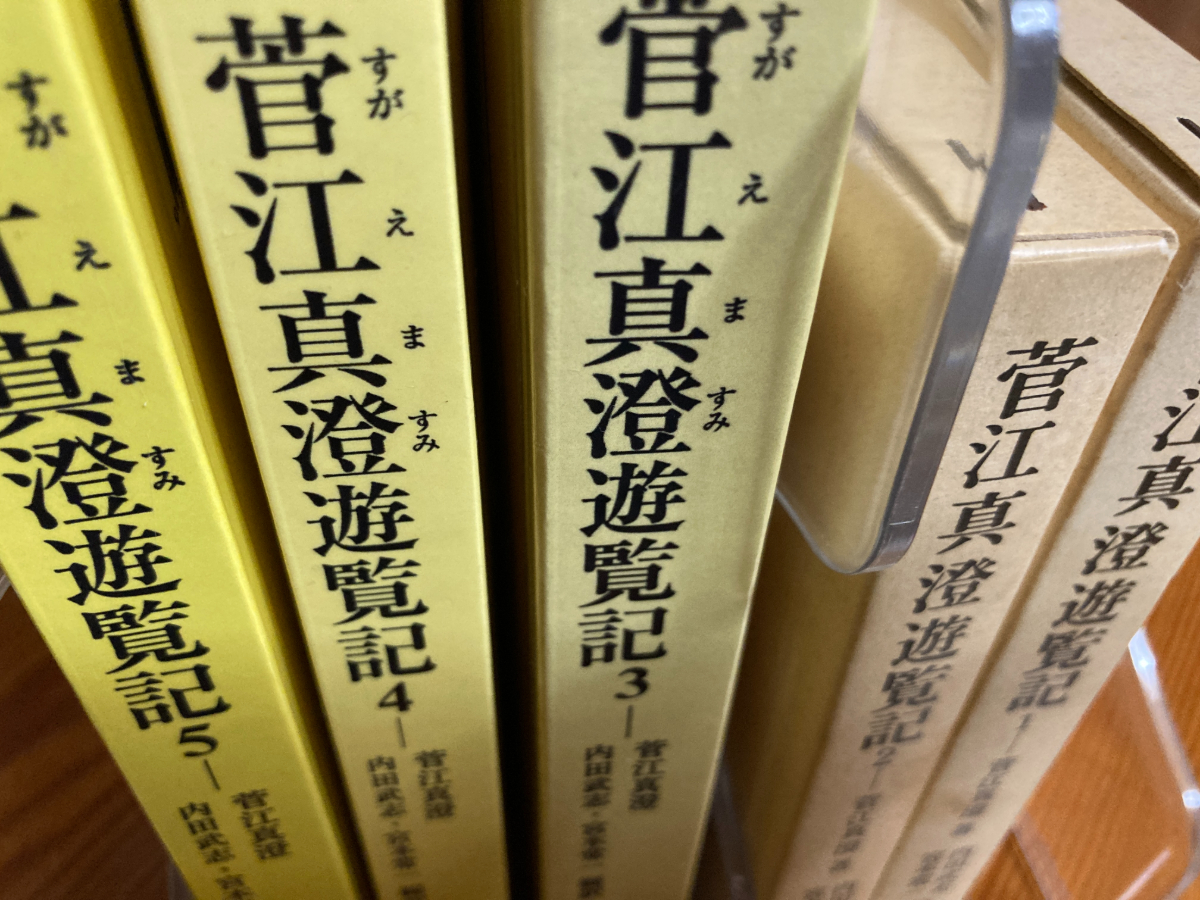津軽の奥について
江戸時代の紀行家菅江真澄の「津軽の奥」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政7年(1795)の旅です。
真澄は、津軽に入り、小湊、浅虫、青森を経て弘前に行きます。翌年の正月は小湊にいます。その後弘前に滞在して岩木山に登ります。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政7年3月22日は新暦では5月10日にあたります。日記が終わる寛政8年3月2日は4月9日にあたります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「津軽の奥(一)(二)(三)(四)」からの引用です。
寛政7年3月22日
夏泊半島の椿崎をみようと思い、南部藩の馬門の関を越えます。次いで狩場沢の関を越えて津軽に入ります(南部藩と津軽藩の藩境塚)。
菅大明神の祠、ほれさしという川、口広村、清水川村、浜子を経て雷電の林が見えるところにきます。
神明の祠、小湊、雷電院日光院という修験者に会い、小湊の問屋、宮島某に宿をとります。
3月23日
朝早く案内人をたてて出立します。福島村、福館村、山口村、平川村、雷電の祠(雷電宮)、浅所村、間木の浜、滝村、鎧崎の坂、立石、ヘツケナイ、穴沢という崖、白砂村、しらす越えの坂、鎧崎を経て、田沢の村で浦長の家に宿をとります。
3月25日
田沢に滞在しています。雨が降っていますが晴れ間に近くを歩きます。館跡があります。
3月26日
晴れたので椿崎を見にでかけます。椿山を歩き椿明神(椿神社)に詣でます。神社の縁起を書いています。
久地の浜を過ぎて、大島(大島)を眺めます。稲生、小稲生、浦田を経て、茂浦に着きます。この辺りがすばらしい景色なので泊まって夜明けの風景をみたいと宿をもとめましたが「一人旅に宿をみだりに許してはならないという、このところの定めであるから」と言って誰も泊めてくれませんが、ようやく人情のある老人が宿をかしてくれます。夕飯にふくべら(ニリンソウ)、しおで、くまあざみを煮たものと今日摘んだという海苔を出してくれます。島々が波の上にそろってたゆとうように夕日に映えて趣があります。
3月27日
板橋という山里を経て土屋(土屋番所)の浦の景色のよい岡を越えるところに「かんかけ」があります。浅虫、うとうまえのかけはし(善知鳥崎)、へびつか、笊石の浦に入って、この地の景色があまりにおもしろいのでここに宿をとります。
10月15日
青森に滞在しています。弘前の知人から誘いがきて訪れることにします。
青森の港辺を出立して南に向い、浜田、妙見菩薩の林(大星神社)、やちやく、荒川村、荒川山宗全寺と歩きます。宗全寺で古い柳をみてたたずんでいると僧が出てきて「二月、三月にはこの柳も姿、風情がすばらしい。そのころ必ず訪れてきなさい」と言います。高田村を経て、雌狸(まみ)の坂(大豆坂・まめざか)まで行きますが、日が暮れてきたので小館または中野という村に入って村長の家に宿を頼みます。
10月18日
雨、雪に降こめられて数日小館に滞在しています。夕方、酔い泣きしながら三、四人の荒くれ男が入ってきてうたいわめきながら寝てしまいます。
10月19日
晴れたので出立して入内に行こうと家を出ます。通りかかった木こりが案内してくれます。くくりひめの祠(白山)、薬師仏の堂を経てあるきます。日が暮れようとし雨も降ってきたので、田山という村の建て直し途中のあばら家に許しを得て泊まります。寒さでなかなか眠れません。朝になって炉のそばにいくと若い男が「寒さで眠られず起きてきたのでしょう」と芝をつぎたしてくれました。
このとき真澄は、「鳥がなく東のくにの陸奥の小田なる山にこがねありとは(大伴家持)」の小田の山を、耕田の山(八甲田山)と推測して、近くのこがね神社が黄金山の神を祭った神社であろうと推測します。
10月20日
雪が降るなか雪をかきわけて、こがね神社(小金山神社)に詣でます。馬で泉沢を行き、昼ころ王余魚沢(かれいざわ)に入りますが、これ以上進めず、一休みした家に泊まることになります。
10月21日
昼ころ出立しますが、吹雪で進めず、下かれい沢というところで民家に入ります。そこの主人が「この雪のなかをひとりで行かれては危険でしょう。火にあたって休み、晴れ間をみて出かけてゆくなり、このまま雪にふり暮れたなら今夜はお泊りなさい」と親切に言ってくれます。
10月22日
晴れたので出立します。御鐵漿(おはぐろ)平、五本松を経て浪岡八幡(浪岡八幡宮)にきたころすさまじい吹雪になります。立ちどまり立ちどまりして女鹿沢村について、休もうとある家に入ると主人の福士某が「この雪にどうして行かれよう。晴れるのをまちなさい」と泊めてくれます。
10月23日
ここで受けた情ぶかいもてなしを、いつかは報いようと思いながら出発します。貢(みつぎ・水木)に着きます。毛内茂粛の家を訪ねます。「一、二日はここに滞在しなさい」と親切に言ってくれます。この家に斎藤規房という人がきています。
11月1日
貢の村を出立し、以前親しく語り合った間宮祐真を訪ねて竹が鼻(浪岡町)に向います。下十川、福島、馬場尻、小屋敷、飛内、二双子(にそし)、増館(高館)を経て竹が鼻に着きますが祐真が江戸に行って留守なので戻ります。
途中道に迷って、高館まで戻って、ちいさな家をたずねて焚火にあたらせてもらいます。主人が「このような雪のなかに行き暮れては、生命も危険でしょう。宿をおかしするのは容易ですが、しかし何をきせて寝かせたらよいかそれが心配です」「それがいやでなかったら、おやすみください」とすすめてくれたので泊まることにします。
寝てから夫婦が話しているのが聞こえます。「これは、どこの人だろうか。この山奥の大雪にまよい出て、こんな乞食の小屋のような家にふりこめられて寝たなどと聞いたら、家族のものは、さぞつらいことだろう」これほどまで、思いやりのふかい心づかいを父母がするものかと、涙があふれてきます。
11月2日
黒石に行こうと出ましたが、まだ人が通ったあとがなく、雪もふっているので、昨日たどってきた道を戻って、二双子村につきます。とある家のなかから「見たことのある人のようだ。さあお寄りなさい」と声をかけてくれたのは昨日出会った館山養泊という医者でした。家に泊めてもらいます。
11月5日
雪が降りつづくので館山の家に滞在していました。昼ころ黒石に行こうと館山の家を出立します。野際村、ぐみのき村を経て黒石に入り、高田恵民という医者の家をたずねて泊めてもらいます。
11月7日
紫雲山来迎寺の松を見に行きます。
11月8日
高田の家をでます。宝厳山法眼寺(法眼寺)、福民、牡丹平、花巻、小石(こな)坂、豊岡、中村、築館、新路を経てぬる湯(温湯温泉)の村に入ります。古沢という家に泊まります。故郷の夢をみます。
11月14日
黒石を出立して、浅瀬石川を渡り、尾上に入り、吹雪のため一休みしてから猿賀神社(猿賀神社)に参拝します。
日沼、和徳、稲荷の祠(和徳稲荷神社)を経て弘前の町に入り、問屋の前田という家に宿をかります。
11月15日
藩校の稽古館、法輪山真教寺で行宅翁の墓にたむけをして、毛内茂幹の家を訪ねます。歌を応酬しあって日を過ごします。
11月24日
青森に向かって出立します。斎藤規勇の家に寄ったら子の規房がいるので誘って一緒に出ます。
堅田、撫牛子、大久保、津軽野を経て百田にきて橋をわたります。藤下(ふじしま・藤崎)、堰神(堰神社)、葛野、矢沢、八幡の神社(矢沢正八幡宮)、を経て水木村に入り、毛内の家に泊まります。
11月25日
午後になってから出立します。増館、川倉、十川を経て女鹿沢に入り、知人の家に泊まります。
11月26日
草そりというものにのります。箱ぞりに似ています。四人が引き綱をとり、うしろから二人が押して進みます。
杉沢、高屋敷、徳才子、大釈迦、杉野沢、津軽坂、毛なし平、坊主ころがし、戸門、白旗野を経て新城に着きます。
新城から馬で岡町を経て大浜に入ります。神主沢田兼悉を訪ねます。
11月29日
大浜を出て、昼ころ青森に着きます。
寛政8年1月15日
小湊(平内町)に滞在しています。
小豆のかゆを食べおわるころ、田植えをするといって、稲の茎に豆がらをまぜてたばね、雪をかきならして植えます。やがて、枡に濁酒のかす、米ぬか、豆の皮をいれて、「豆の皮ほかほか、銭も金もとんでこい。福の神もとんでこい」と唱えて家のすみずみを巡ってまきます。
女の子がはいってきて「春のはしめ、早乙女がまいった」というと、みち、銭を与えます。男の子がきて「春のはじめにたちどがまいった」いうとものを与えます。
1月16日
小湊に滞在しています。早朝、男たちが、鳥追いのしぐさをして、笛、つつみ、おしきの底をうちたたき、拍子をとって「朝鳥はより、夕鳥はより、長者どののかくちは、鳥は一羽もいないかくちだ。はよりはより」と巡り歩いています。
1月20日
小湊に滞在しています。今日はめだしの祝です。子供たちが賽を投げて遊んでいます。
2月1日
小湊に滞在しています。一月と同じく正月祝をしています。松をかざりしめ縄をひきまわしているのは厄年の人がいる家です。
3月1日
弘前に滞在しています。毛内茂幹が百沢に行くのに同行します。駒越の渡しで岩木川を渡ります。将棋の駒のかたちをした舟をひいて渡しています。
熊島、旗鉾、高屋、賀田、蓮住院、城の跡(大浦城址)、御台、老母(ばこ)橋、山崎、武南方彦命の祠、新法師を経て百沢に入ります。
小法師の案内で百沢寺(岩木山神社)の境内を巡り下居の宮に詣でます。
岩木山の山頂に登ります。百沢寺に泊まります。
3月2日
高照霊社(高照神社)に詣でます。高岡、新法師、賀田、こまこし川を渡り(岩木橋)、毛内茂幹と別れて斎藤規勇の家に着きます。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ