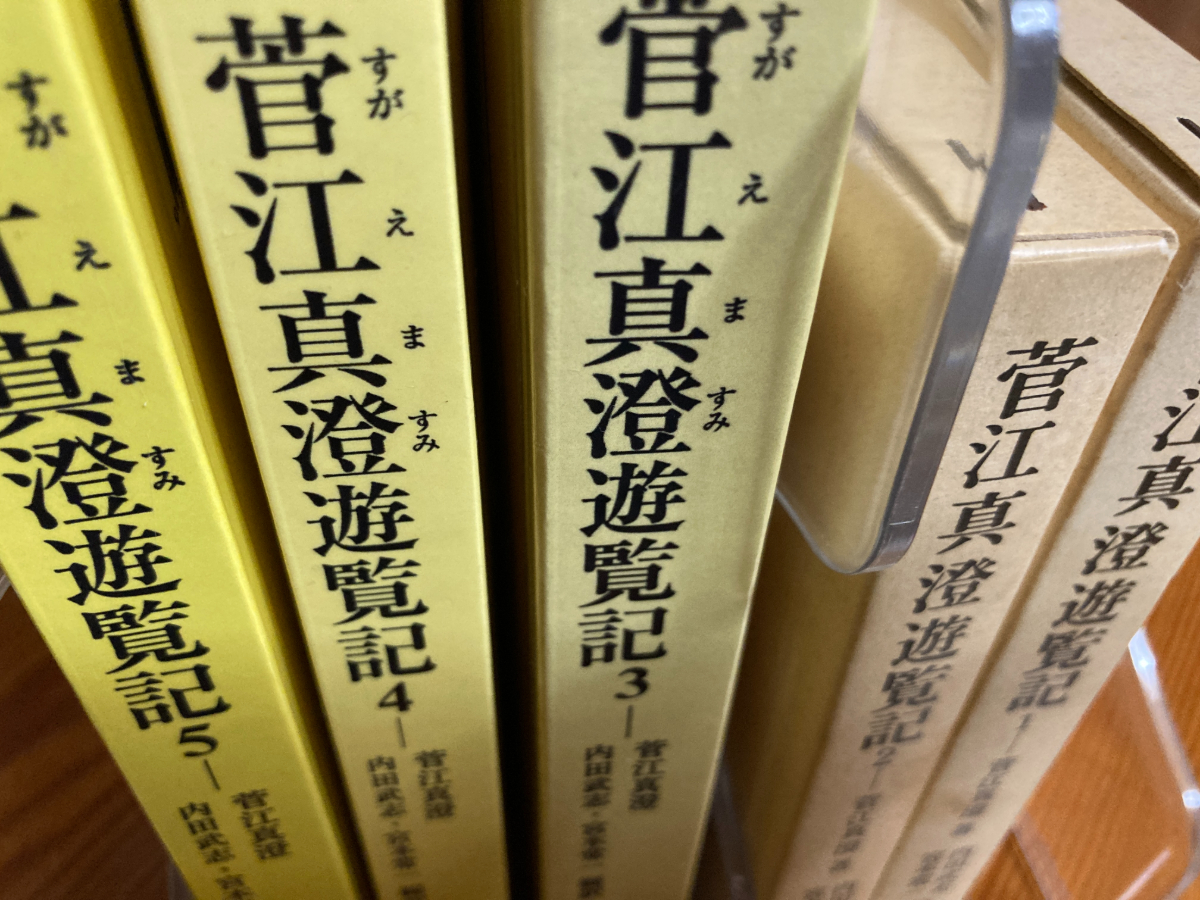奥の浦うらについて
江戸時代の紀行家菅江真澄の「奥の浦うら」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政5年(1793)の旅です。
菅江真澄遊覧記では「奥の浦うら」の前は「牧の冬枯」ですが、間に「えぞがいわわや」という日記があるそうです。日記そのものは所在不明ですが、他の資料から、雪が消えてから尻屋崎を見に行き田名部にもどらずに津軽海峡沿いに佐井に移動したことがわかっています。
4月1日、佐井に滞在していた真澄は、佐井から南下して脇野沢に至り、川内、城ヶ沢を巡って田名部に戻ります。その後、恐山にのぼります。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政5年4月1日は新暦では5月10日にあたります。日記が終わる6月25日は8月1日にあたります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「奥の浦うら」からの引用です。
寛政5年4月1日
佐井に滞在しています。
佐井から小舟に乗って弁天島、矢越岬、かんかけの浦(願掛岩)、磯谷、あなま、長後、長浜、福浦山、入道石、仏がうだ(仏ヶ浦)、極楽はま、てんがい石、うし穴を見ながら牛滝で舟を降ります。
「近くを行く釣舟の舟のりたちは盃をとりながら、肴になにがよいかと、とったばかりのあわびを生のまま食っているようだ」というのどかな風景です。
村長坂井某の家に泊まります。この家で佐井の医者三上温と会い、語り合います。
4月2日
牛滝に滞在しています。神明社、弁財天の祠、真如庵に詣でます。
4月3日
牛滝に滞在しています。うし穴のあたりを散策します。
4月4日
小舟に乗って近くを巡ります。仏がうだを過ぎて、極楽浜で降ります。また小舟に乗って福浦で降ります。三上温とここで別れます。真澄は山路を歩きます。長後、あなま、磯谷、ほんたの神(矢越八幡宮)、神掛・鍵掛、矢越を経て佐井に着きます。しなたの家に泊まります。
4月5日
一日中雨が降っていましたが夕方の晴れ間に松齢山法性寺の桜を見に行きます。
4月6日
亀井山発信寺の珠阿上人を訪れます。昨夜の雨で水かさが増して、山から切り出した木材が流れて海面にただよっているのをたくさんの小舟がでて拾い集めているのをみます。
4月12日
佐井に滞在しています。このあたりの磯辺に多い材木石を花壇のしきり、屋根のおさえ、短くして寺の土塀に活用しているのをみます。
4月16日
浦々を巡りながら田名部に帰ろうと佐井から小舟に乗ります。ごんべ島(弁天島)に上陸して弁天に詣でます。糠森で舟を降ります。かんかけ、磯谷を過ぎて山道をたどります。
かんかけ(願掛岩)で、鳥居に桜の大枝を折ってつくった「かぎ」が掛けられているのをみます。津軽の岩木山を眺望して「清見潟(静岡県清水市)から三月に富士山を眺めたようである」と感嘆しています。「道行く友は、しばしば休みながら」と書いているので同行者がいたようです。
長後で夕食後、スルメイカを釣る小舟の漁火をみます。長後で宿泊します。
4月17日
雨が降ってきたので宿泊先の主人から出かけない方がよいと言われますが、晴れ間が見えたので出立します。鉛の鋪穴(抗口)などをみて、長浜、大黄楊の山坂を経て福浦に着いて宿泊します。
体調が悪いようです。強風が吹き「屋根のそぎ板も吹き散らすほど吹きまくり」眠れません。風邪ごこちも重くなってきました。
4月18日
牛滝越えをするという子供の案内で福浦を出立します。「子供が友だちにかたっている」と書いているので一人ではないようです。牛滝を目指して山道を行きます。「罪を犯したものは、男女の区別なくこのあたりに流される」ところだと書いています。
風邪でだるく、休みやすみ進みます。牛滝の坂井の家に着くと、昨日舟できたという珠阿上人、渋田政備、医者三上などがいます。宿泊します。真澄は体調が悪くて日暮れ前に寝てしまいます。
4月20日
牛滝に滞在しています。風邪が重くなって渋田、三上が帰るといっても起きることができません。
4月27日
日記が再開されました。おそらくずっと寝込んでいたと思われます。
きょう牛滝を出立したいというと、珠阿上人が別れを惜しみます。真澄は小舟に乗って、小つなさかり、大つなさかり、小荒川を過ぎ大荒川で降りて、山道を行きます。行っても行っても里がないので迷ったのではないかと不安になります。
おおやまずみの神の社を経て源藤次郎(源藤城)についてほっとします。潟貝という村に桃の花園があります。滝山では老婆が「この山里は、鹿、猿がおろけて(あばれて)粟穂、豆、蕎麦など、みなしごいて食うので」と嘆いています。暗くなってから脇野沢(愛宕山公園)に着きます。村長のところに宿泊します。
4月28日
脇野沢に滞在しています。この辺りにむかし蝦夷が住んでいてその子孫がいるという話しを聞きます。
4月30日
近くを見ようと歩きます。土橋から鶴首山に登り、をたき(愛宕)社(愛宕山公園)に詣で、尾根伝いの道を歩きます。新井田、木浪、蛸田、芋田と九艘泊までの道のりを書いています。木浪までは行ったようですが、九艘泊(九艘泊漁港)まで行ったかどうかは文面からは確かでありません。
5月1日
脇野沢を出立します。端午の節句の幡のぼりが門々にたっています。神明社(脇野沢八幡宮)、松が崎(松ヶ崎石神邨社)、口広川、小沢、殿崎、古城の跡(蛎崎城趾)、飯形(いなり)の社、姫小松(蛎崎八幡宮)と歩きます。
蠣崎の里を過ぎようとするとき、通りすがりの人が「ここに鷺の湯というよい温泉がある」と教えてくれます。
めくら川という小川をわたって宿野部にきました。さらに檜川をわたり、葛沢、川内と歩きます。観世音を神としてまつる庵の前で満開の桜をみます。たいそう広い川(川内川)を唐櫃のふたのような舟でわたります。船頭は唐の国に漂流して帰ってきたと身の上を語ります。川をさかのぼると銀杏木という里があり金七五三(かなしめ)明神という古い社があることを聞きます。川内で宿泊します。
5月2日
昼になってから出立します。村はずれに熊野社があります。ここから二、三里行くと湯の川(湯野川)というよい温泉があると書いています。田野沢、戸沢村、角違、泉沢・一里越を経て、城が沢で宿泊します。
5月3日
朝早く出立します。里のはずれの森に神明の社があります。宇曽利川、宇田村、川守村、釜臥山をまつる下居の宮(兵主神社)を過ぎます。芦崎が荒波をさえぎり「冬は鱈つり、春はにしんの網を引いて、村は豊かで」と書いています。大平、願求院、三日月堂、肥泥(ひどろ)村、金谷を経て、えび川を渡って田名部に入ります。
5月5日
田名部に滞在しています。「笹の粽(ちまき)に「ほど」の根を食い」などと端午の節句の様子を書いています。
5月6日
田名部に滞在しています。男と女が戸外にたたずんで「たわむれ」を言っているのを聞いています。
5月14日
田名部に滞在しています。田の土をこまかくするために馬を引いて田のなかを巡っているのをみています。
5月15日
田名部に滞在しています。中島公世の弟である医者徳広が脇野沢に行くのを見送ります。桐の花を子供が拾って笛のように吹き鳴らしているのをみます。
5月16日
薬草取りに誘われて、石神、願求院跡、田屋を歩きます。
5月20日
田名部に滞在しています。このあたりは稲田より稗田が多いと書いています。
5月25日
恐山(恐山)に再び登ろうと、中島公世と相談して出かけます。材木をのせたたくさんの牛とすれ違います。
5月26日
恐山の菩提寺に泊まっています。湯浴みの様子を「女は紺の湯まきをして大ぜいならび、頭に手拭をかけ、大きなかいけ(手桶)というもので湯をさかんにすくい、これをかぶるといって、百度も千度も頭にうちかける」などと書いています。
5月27日
太師堂の近くで槲石(かしわいし=カシワの葉の化石を含む石)、舎利石(しゃりりいし=栗の大きさで真珠に似ていたと書いています)を土産にと拾います。田名部に帰ります。
6月1日
田名部に滞在しています。今日は氷室の祝で、氷餅(干し餅)などを持ち歩いて贈答し合っているのをみます。
6月2日
湯浴みをしようと恐山に向かいます。前日から智愚庵に泊まって、実元上人、秋浜某、ひきど春花法師などと暗いうちから出かけるつもりでしたが、雷がなり雨が降っていたのでしばらく見合わせましたが晴れたので出立します。
途中、雷を聞きますが、それは板敷きのように木を敷きならべてつくったかけはしのような道を馬が行く音でした。
恐山について姥堂(うばどう)という建物に大ぜいの人と寝ます。
6月5日
恐山に滞在しています。窓をあけはなして、ひきど法師や実元上人が琴をかきならします。通りかかったくぐつ(遊女)らしい女が興味を惹かれて入ってきたので、弾くようにうながして弾いてもらいます。
6月6日
恐山に滞在しています。朝、読経が聞こえ、優婆塞、修験者が起き出し念仏をとなえます。この日の恐山は霧におおわれていました。
6月7日
恐山に滞在しています。里から登ってきた人が、昨日、岩屋の浦(東通村)にロシア人がきたことを伝えます。
6月10日
恐山に滞在しています。昼に雨があがったので、近くの辺りにでかけます。暑い六月でも朝夕は重ね着をするほど涼しいなどと気候について説明しています。
6月23日
恐山に滞在しています。恐山は地蔵会(え)の日です。各地の村里から大ぜいの人が集まってきます。卒塔婆塚の前に棚がつくられて花が飾られ、七の仏の幡をかけて、あか水が供えられています。人々は柾仏(檜の柾板に祖先の戒名を書いたもの)を御堂で六文で求めてこの棚に置いて祈ります。「日が暮れると大ぜいの人々が群れあるき」「うば堂、食堂、尊宿寮、小屋などまで、たくさんの人が入り、いっぱいに満ちあふれているので寝るところもない」と混雑ぶりを書いています。
6月24日
恐山に滞在しています。夜が明けていくころ、たくさんの人が数珠をもみ、わが子わが孫の亡き魂をかぞえあげては涙をおとしています。夜が明けると円通寺の高僧が払子をとって誦経してまわり、魂棚にこられるとみな寄りつどってきます。
馬をひいて迎えがきたので田名部に戻ります。
6月25日
田名部に滞在しています。松杉の林に虫が大発生しています。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ