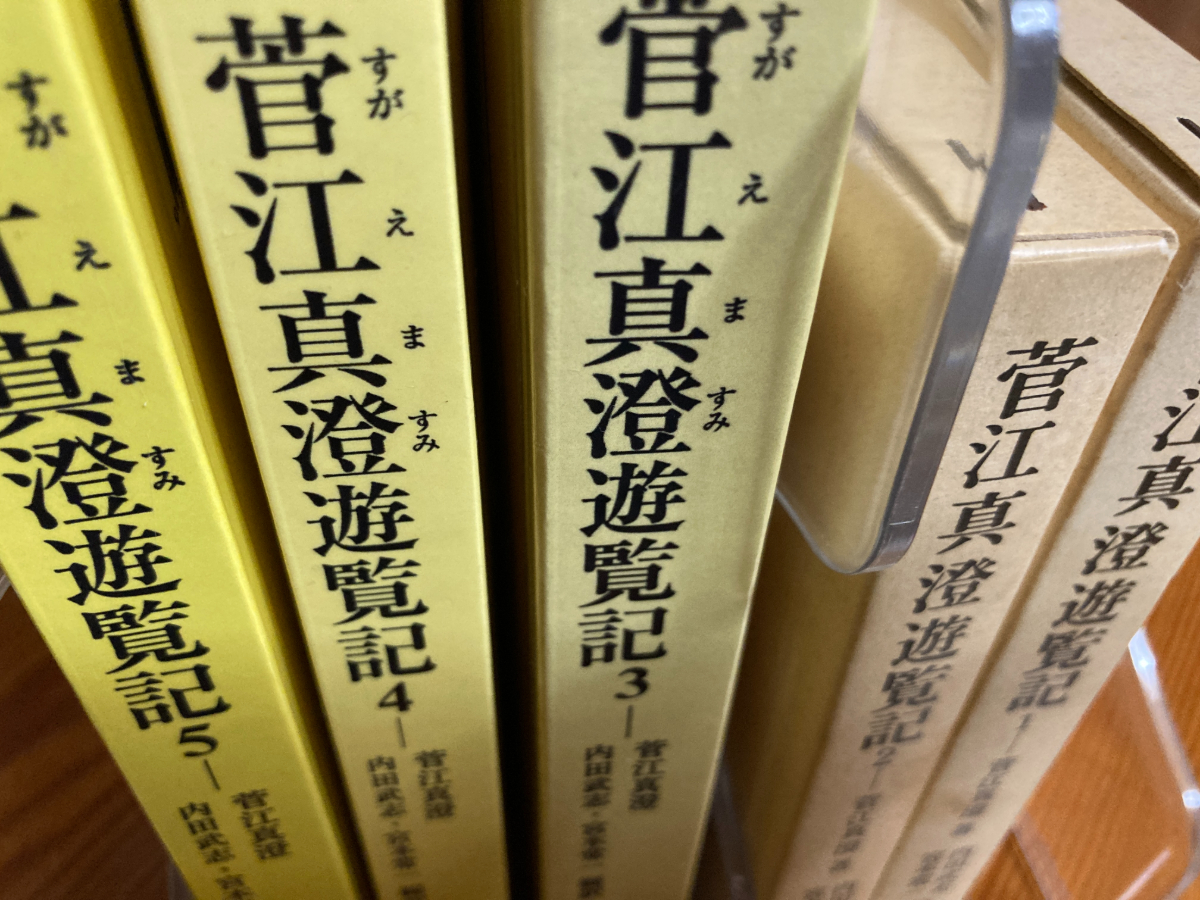牧の冬枯
江戸時代の紀行家菅江真澄の「牧の冬枯」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政4年(1792)の旅です。
菅江真澄は滞在していた北海道を出立し、下北半島の奥戸に入り、大畑、田名部などで過ごします。恐山に行ったほかには目立った動きはありません。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政4年10月7日は新暦では11月20日にあたります。日記が終わる12月30日は翌年2月10日にあたります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「牧の冬枯れ」からの引用です。
寛政4年10月7日
松前の福山の東、泊川から船出します。夜、下北半島の大間崎(大間崎)近くの奥戸(おこっぺ)という浦に着について、小谷という家に宿泊します。
10月8日
奥戸から矢根杜(やのねもり)の神社をめざします。南下して、赤石、材木村、原田を経て佐井に着きます。弁財天が祀られている小島をみて、神明社に詣でると、滋眼山清水寺があります。川を一つ渡って矢根杜(箭根森八幡宮)にのぼります。
10月10日
奥戸を出立して大畑に向かいます。浜道を行けば大間崎を通りますが、大間の牧のなかを通る中山越の道にします。
大川目、小川目、小奥戸、大間の牧、佐賀森、五輪田(ごりんだ)のくぐり岩、釜谷の浦(蛇浦)、異国間(易国間)、日かけ山、杉ノ尻、桑畑、作馬台、枝折崎(日和崎)、長浜、下風呂(下風呂温泉)、甲(かぶと)崎を経て赤川につきます。「赤川という里は山川の水が赤かった」と書いています。
この近くには「ちぢり浜」という名所があるのですが、立ち寄らなかったことを後に残念がっています。釣屋浜(つりやはま)、由阪(ゆさか)を経て川(大畑川)を舟で渡って大畑に入り、堺某の家に宿泊します。
10月21日
故郷の夢をみて歌を詠んでいます。
10月22日
「恐山にのぼりたいと思い、このごろずっとこの里に滞在している」と書いています。恐山に詣でるには田名部からが良いと聞いてこの日田名部に向けて出立します。正津川村を経て関根につきます。関根では「ぬかるみの道をはるかに遠くまで丸太を敷きならべてあるので梯子の上をわたるようにらくにたどられる。これはほかの国ではみたことがない」と感心しています。樺山、女館、栗山を経て田名部(むつ市)に入ります。新相(にいあい)某という旅館に宿泊します。
10月29日
田名部に滞在しています。「雪は日増しに多く」と書いているので大雪にはばまれて恐山にのぼれないでいるようです。
町の様子を「この里のならわしで庇(ひさし)を広く作り、その軒端ばかりを行きかいするので、売り買いする人はらくにあるいている。」と書いています。田名部にもガンギ、コミセがあったようです。
10月30日
ようやく山の湯(恐山)に行くことになりました。二股川を経て長坂に行って眺望の良いところから尻屋崎や大畑の浦(津軽海峡)を眺めます。また、芦崎、安渡の入江(大湊湾)、対岸の野辺地の浦うら(陸奥湾)が見わたせた、と書いています。今のむつ湾展望駐車場のあたりから津軽海峡と陸奥湾の両方が見渡せます。
冷水(冷水)を経て宇曽利湖畔につきます。を経て恐山(恐山)につきます。老法師が出迎えて炉に太い薪を積みかさねて暖をとってくれます。
11月1日
恐山のあちこちを巡り詳しく描写しています。この日、田名部に戻ります。田名部は月に三度の市日(田名部は一が付く日が市日)でにぎわっています。
11月14日
田名部に滞在しています。つまご、わらぐつといって、雪道をわけてゆくためにつくった履物を売る男をみています。
11月15日
田名部に滞在しています。「回覧状をもってあるくひとを参語(さんごう)といい」など地元の様子を観察して書いています。
11月18日
田名部に滞在しています。蕎麦がきに小豆を入れた「はっとう」をこの辺りでは「せんぞうぼう」というと書いています
11月20日
田名部に滞在しています。七十あまりのぼけた様子の法師をみかけて狂っているかと思いますが、人の生死をあてる力があり、人々が「ありまさ(神がかりするもの)」と呼んでいると知ります。
11月21日
田名部に滞在しています。松前にいたときの知人から心のこもった手紙と綿入れの着物が届きました。花子という少女が書いた手紙も入っていました。書いてある歌が稚拙であっても「真実、相手を思っている心は他の人のまねることもできないもの」と感激して返歌を送っています。
11月22日
田名部に滞在しています。女の子がたくさん集まって雪なげをして遊んでいるのをみます。女の子たちは道を行く法師の頭にまで雪をぶつけていました。
11月23日
田名部に滞在しています。大師講の日なので、大師様に柳の枝で作った三本の棒をそえて粥を供えます。その柳の枝を折っているのをみます。
11月26日
田名部に滞在しています。子供らが囲炉裏にきて灰をかきならして「へんつき」という遊びをします。「へんつき」は、板の切れ端などを「炉のなかにたてて遊ぶやり方と書いています。
12月1日
田名部に滞在しています。「鱈(たら)よ安渡鱈(あどたら)よ」など、物売りの売り声を採録しています。
12月2日
田名部に滞在しています。朝に地震があったと書いています。この月28日にあった大地震の前震かもしれません。
12月3日
田名部に滞在しています。知愚庵の主人実元上人を訪ねようとでかけたら、子供たちが大ぜい集まって、「杖のようなものにまたがり、竹うまのようにのって、凍った雪のなかをつぶてがとぶように下って」遊んでいるのをみます。
12月4日
田名部に滞在しています。川が凍っているのを橋の上から眺めます。
12月5日
徳元寺(徳玄寺)の寂隆上人を訪ねます。古い鏡で穴が三つあいているのを見せてもらいます。
12月13日
大畑に向かいます。樺山、なごの林、円仁大師の石経塚、平等庵を経て大畑に入ります。
樺山で牛飼いの子が牛を扱っているのをみます。また、樺山の女性の服装を観察しています。正津川の村長が優婆堂に案内してくれます。雪が降りつのって「いま来た方角も行く手も見えない」状態になりますが、なんとか夕方に大畑につき、田中某の家に泊まります。
12月16日
大畑に滞在しています。津軽の港をでた船が遭難して長後、牛滝の荒磯に流れ着いたものの狼に食われた話しを聞きます。
12月19日
田名部に向かいますが途中で吹雪になります。正津川で老婆が「うざねとりて(辛労をいう)こんな道を行くよりも、きたないところであるが、わたしの家に一夜お泊りなさい」と声をかけて泊めてくれます。
12月20日
朝、人通りがあるようになってから出立します。村はずれの坂で大ぜいの子供たちが橇(そり)で遊んでいるのをみます。うすぐらくなって田名部に着きます。
正津川から田名部までは約13キロ、通常であれば徒歩3時間の道のりです。雪道で難儀したとみえてずいぶん時間がかかっています。
12月22日
田名部に滞在しています。「すすとり」という大掃除をしている家が多いと書いています。
12月23日
田名部に滞在しています。節分です。豆をまく男が家屋敷のすみずみまで豆をうっています。
12月24日
田名部に滞在しています。立春です。
12月25日
秋浜武憲の家を訪ねます。主人が盛岡の小本尚芳という人の歌を見せてくれます。垣の外でしている世間話の内容を書き留めています。「三年婿」はどうしたかという話題です。三年婿五年婿というのは年数を区切って婿に入ってその家の主人になり、約束の年がくると嫁を連れて自分の家に帰るという、期限付きの婿入り制度です。嫁の家の跡取りがまだ幼い場合に行われることがあったようです。
12月26日
田名部に滞在しています。「としの市」がたって年越しの用意の品々が売り買いされています。
12月27日
田名部に滞在しています。子供たちが竹杖を凍った雪の上に投げる「棒やり」という遊びをしているのをみます。
12月28日
田名部に滞在しています。「正午の時刻を知らせる合図の貝を吹くころ」大きな地震が発生します。「舟などが波にもまれるように軒が傾き、ひしひしと鳴り動き、雪も下からもちあげられて」と書いています。
この地震は「寛政4年12月28日に現在の青森県大戸瀬崎の沖合 13km 付近の日本海を震源として発生したM 6.9から7.1と推定される地震で、元号を冠し寛政西津軽地震や最大の被害を生じた地名から鯵ヶ沢地震とも呼ばれる。(引用:Wikipedia 西津軽地震 2025年2月3日)」
この地震は鰺ヶ沢を中心に津軽地方に甚大な被害をもたらしました。深浦町の千畳敷海岸はこの地震で隆起したと伝えられています。真澄の日記によれば下北半島の田名部でも震度5クラスの揺れがあったようです。
12月29日
田名部に滞在しています。「今日も地震がときどき起こった」と書いています。余震が続いているようです。
12月30日
田名部に滞在しています。夕方また地震があります。子供たちが門門の雪の上にたてた樺の木皮に火をともしてるのをみます。「さいとりかば」といいます。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ