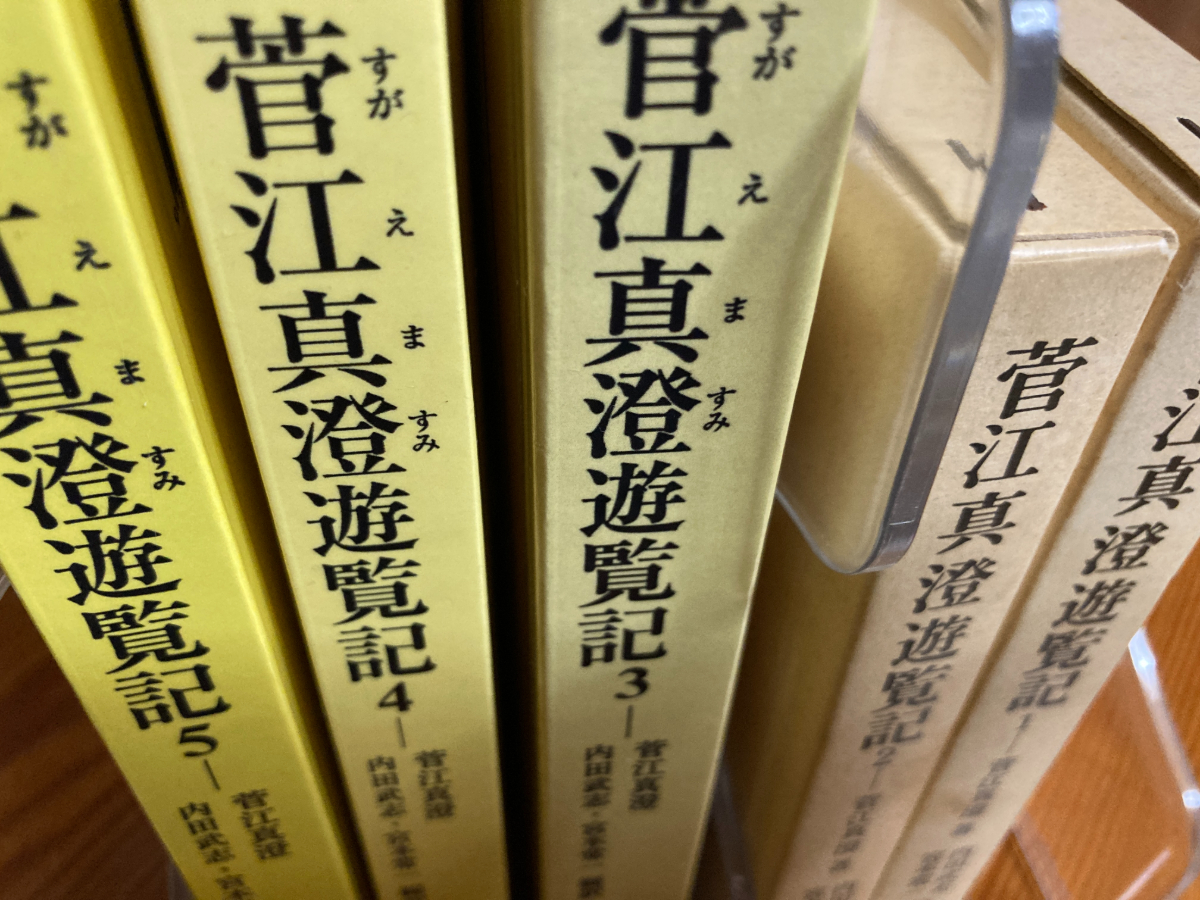牧の朝露について
江戸時代の紀行家菅江真澄の「牧の朝露」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政5年(1793)の旅です。
田名部に滞在しています。近く田名部を出発しようと思い親しい人に別れを告げるために大畑に向います。さらに、下風呂、易國間を再訪しています。このとき、棚部を去って南下するつもりがあったようです。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政5年7月1日は新暦では8月7日にあたります。日記が終わる9月25日は10月29日です。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「牧の朝露」からの引用です。
寛政5年7月1日
正午の貝を吹くころ大畑に向けて出立します。関根から浜辺を通って行きます。波に打ち上げられた昆布を馬牛につけて頻繁に運び込んでいるのをみます。大畑に着いて田中某の家に泊まります。
7月6日
大畑に滞在しています。「まだ暮れはてぬころから、子供らが、六、七尺から一丈ばかりの棹の先に、色どった画をかき、七夕祭と記した横形の燈籠をともして、その上部には小笹、薄んどがさし束ねてあり、それを手ごとにささげ持って『ねぷたもながれよ、豆の葉もとどまれ、芋がらおがら』とはやし唱えながら、太鼓、笛をならして、にぎやかに声をはりあげて歩く」のをみます。「ねぶたながし」、今のねぶた祭です。
7月7日
大畑に滞在しています。今日も「ねぶたながし」が歩いています。七日盆なので家の軒ごとに提灯がかけられています。
7月8日
急用があると伝言があったので馬で田名部に戻ります。
鵜沢(うざわ)というところで、田名部代官所の役人、菊池成章、菊池清茂に出会います。懇意にしている仲なので「どうなさいましたか」と語り合います。清茂は蝦夷地から帰ったばかりで、これから二人で佐井に行くところです。
菊池成章は代官所の役人であるとともに学問にすぐれた歌人でもありました。田名部滞在中は生活すべてにわたってこの人の世話を受けていたようです。
7月9日
田名部に滞在しています。朝夕霧がたちこめています。ことしは田畑のものがよく実るであろうと語っている人がいます。
7月10日
草花を見ようと赤坂野に行きます。川島、中島を通り、午後になると毒が流れるという小川を見ます。
7月11日
大畑に向かいます。今日は盆市で、霊祭に必要なものをつんだ牛馬をひいた人が道のよけようがないほど通っています。
7月13日
大畑に滞在しています。市がたっている町中は盆祭でにぎやかですが、野山の秋をみようと川舟に乗ると風がでて波が高いので、陸路をあてもなく歩いています。釣屋浜、水沢、かんかけの坂を下っていくと滝があります。大沢にある(池田)亀麿の庵を訪れます。そこに泊まります。
7月14日
亀麿の家に滞在しています。まだ明けぬころから謦子をうち小声でお経を唱える声が聞こえます。このあたりの漁家ではたま祭を昨夜ではなく今日の暗いうちに行います。
7月16日
亀麿とともに、かんかけの坂を登り大畑に戻ります。夕方から子供たちが盆踊りをするといって準備していると雨が降ってきます。夜がふけ人が寝静まるころ晴れて、太鼓の音人々のどよめく声が聞こえてきます。
7月17日
明日から行われる田名部の神事をみようと昼に大畑を出立します。途中、若い男女が昨日の盆踊りの楽しさと、昆布をとる仕事のつらさを語っていました。
7月18日
田名部に滞在しています。夜明けからきょうの神楽の準備をしています。浦々村々から燈籠が奉納され、たくさんの机のようなものに小さな神輿が奉ってあります。
7月19日
田名部に滞在しています。祭りの行列を見ます。「さきばらいの声で道路の人をはらいながら、祭の行列がおごそかにねりあるき通り過ぎた。山車にはそれぞれの人形をつくってのせて、紅白のまんまくを引き、四つの車輪をとどろかせ、笛太鼓ではやして、そのあとにみこしが出てきた。」現在の田名部祭です。
7月21日
田名部に滞在しています。常念寺で秘宝を見せてもらいます。
7月26日
大畑に滞在しています。村林某にすすめられて、友人たち三、四人と冠岩に行きます。かな山、小目名村、大山祇の社を経て冠岩に着きます。冠岩を眺めながら岸辺の岩の上に円居(まどい)して弁当を開いて酒を飲みます。
村林某というのは、大畑の村長(遊覧記では村長ですが検断・宿老と記している資料もあります)村林鬼工(源助)のことで、原始漫筆風土年表五十二巻を著した地方の学者でもありました。
7月28日
大畑に滞在しています。この里の人々(優婆塞の某、木村だれ、武田氏喜の子など)と一緒に亀麿を訪ねます。皆で歌作に熱中します。
8月2日
易国間の中井の家を訪れようと亀麿の家を出立します。木野部、赤川を経て下風呂(下風呂温泉)にくると大畑の菊池某がいて泊まっていくようにすすめられます。
8月3日
下風呂に滞在しています。この里の漁師は海にもぐって鮑をとるときに、ふんどしに釣り糸をつけて小鯛をつります。「腰づり」といいます。雨が降ってきたので易国間に行かずに温泉に入っています。
8月4日
下風呂を出て、桑畑、杉の尻を経て易国間に着きます。中井の家を訪れて宿泊します。
8月12日
易国間に滞在しています。女滝川(目滝川)の川上に火がみえて人声がするので行ってみます。子供たちが干した麻がらをたいまつにして鮎やカジカをとっています。「夜とぼしす」といいます。
9月2日
易国間に滞在しています。蕎麦を刈って「はせ」という穂かけ棒などに干しているのをみます。
9月4日
易国間に滞在しています。ある庵で、老女が老法師と話しをしています。
9月5日
易国間に滞在しています。鶯の鳴き声を聞きます。
ロシアからの使節ラクスマンとの交渉にあたった幕府の使者、石川忠房、村上義礼が松前から三厩に帰ってきて、そのまま津軽と南部領の巡視していましたが、この日易国間に到着するというので奉迎の準備をしています。使者たちは午後4時ころ到着します。人々は「貴いお方たちに一夜の宿を奉ること」を喜びあっています。道を清め砂をまいています。どこの家でも菅ごもを敷き、すだれを窓や軒にさげています。肴にあわび、かぜ(うに)、すずき、たなご、かつおなどをたくさん用意しました。
9月6日
易国間に滞在しています。昨日の使者は出立しました。
頭を手拭でつつみ短い汚れた着物を着た二十歳あまりの女が歩いています。出羽の男と来たが、大間の牧場で別の男と通じたため出羽の男が怒って殺そうとしますが、人々から止められて髪を切り着物をはぎとって命だけは助けてやった、といううわさを聞きます。
9月8日
易国間に滞在しています。女たちが鹿が作物を荒らすことを嘆いています。
9月9日
易国間に滞在しています。この日は高いところにのぼるのがならわしだと書いています。
9月15日
易国間に滞在しています。桑畑の神事に詣でようとでかけます。主人(中井)も一緒です。かとの沢、けたの沢、東伝院の跡を経て桑畑に着きます。稲荷の祠で優婆塞がほら貝を吹き、鈴を振って般若経を読んでいます。日が暮れたのでここに泊まります。
9月16日
易国間を出立して下風呂に向かいます。主人は「このようなむさくるしい住居でも、おいやでなかったら、お通りのときはいつでもお泊まりなさい」と言ってくれます。
釜の前、ふた川、おほゆるみ、こゆるみ、くろさき、つぶた、さくま、さいとう、やけ山、なかばま、しをりさき、を経て下風呂に着きます。休憩のつもりでしたが風邪をひいたらしく頭痛がするので宿泊します。
9月18日
下風呂に滞在しています。山かげにある新湯に行きます。漁師たちから沖にでて釣りをしていた舟に蜘蛛の糸が飛んできたという話しを聞きます。
9月19日
下風呂に滞在しています。黒森が岳の神事を見にいきます。
黒森山はむつ市大畑町にある標高420メートルの山です。今でも山頂に祠があり、黒森大権現と刻まれた石碑がたっています。真澄は木野部(きのっぷ)から登ったようです。」
山を下って大沢の亀麿の家に行って泊まります。
9月21日
大沢に滞在しています。たくさんの人が出て山野にいる放馬を柵のなかに追い込む日です。「おのとり」と言います。
9月22日
大沢に滞在しています。風が吹くのでもう一日ととどめられて泊まります。故郷を思う歌を詠んで寝たら故郷に帰る夢をみます。
9月23日
大沢の亀麿の庵を出立します。たくさんの人が野とりの馬を田名部に引いていくのをみます。大畑に着き田中の家に宿泊します。
9月24日
大畑に滞在しています。牛を引いていた子供があやまって垣のやぶれから牛を「かくち(屋敷のうしろ)に入れて家の主人に叱られています。
9月25日
大畑に滞在しています。ある寺で「こめあられ(米をいってあられのようにしたもの)」をいただきます。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ