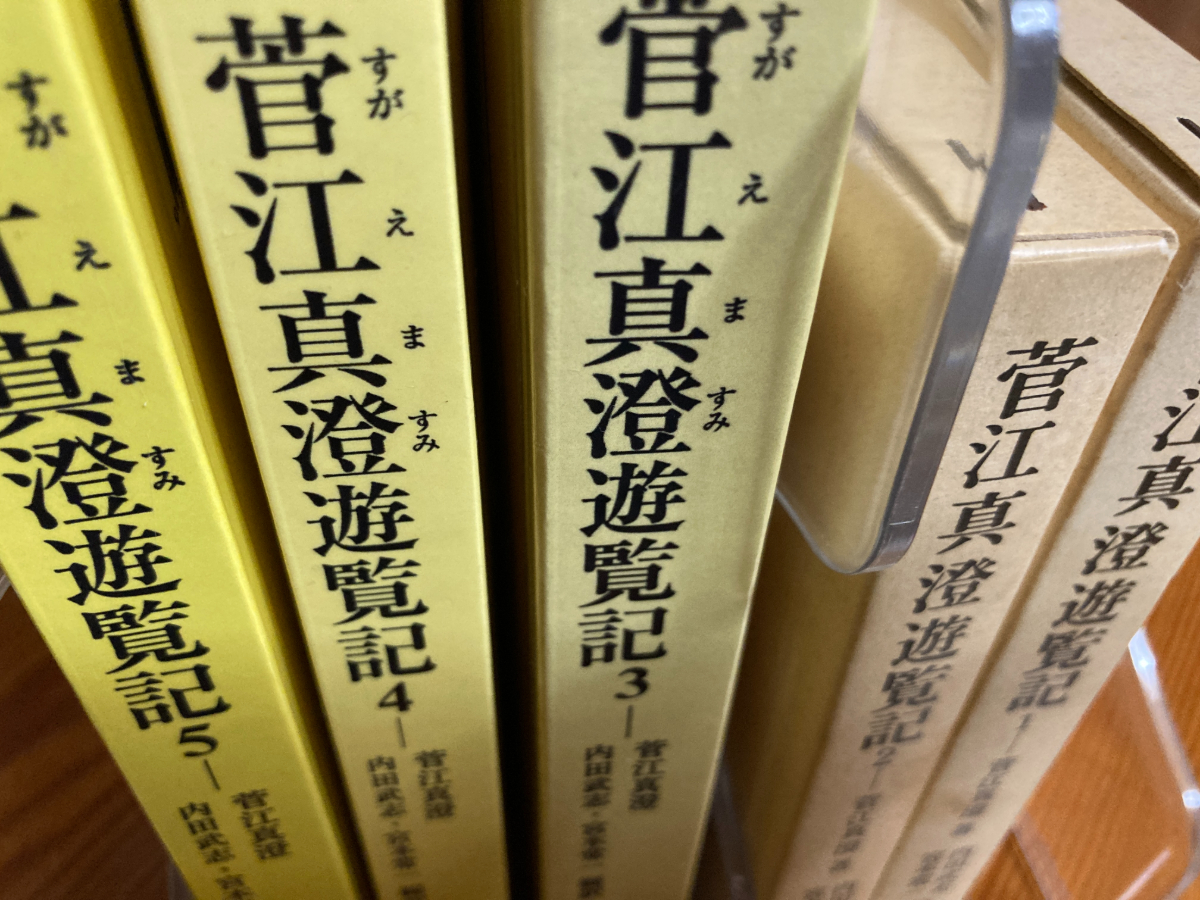奥のてぶりについて
江戸時代の紀行家菅江真澄の「奥のてぶり」に出てくる通過地や滞在地をだどります。寛政6年(1794)の旅です。
田名部で二度目の正月を過ごします。恐山に登り杣小屋に泊まります。
文中の日付は旧暦です。なお、日記が始まる寛政6年1月1日は新暦では1月31日にあたります。日記が終わる3月25日は4月24日にあたります。
なお、真澄はこの年の夏に今の上北郡から三戸郡の辺りを旅しています。その旅の日記「千引の石」「牧の夏草」は未発見です。またこの年の冬の日記「奥の冬ごもり」は東洋文庫版には収録されていません。なので、「奥のてぶり」の次は「津軽の奥」になります。
以下、東洋文庫版菅江真澄遊覧記3「奥のてぶり」からの引用です。
寛政6年1月1日
田名部に滞在しています。南部氏の先祖が甲斐国から陸奥に入ったとき、正月の支度がととのわず、一月一日を前年の大晦日としたことがある故事にならって、今でも元日になってもまだ年が明けていないことになっています。
1月2日
田名部に滞在しています。暦の上では二日ですが、南部領では元旦です。午前二時すぎから起き出して、「麻の上下を着て、燈火をもち、たくさんの人々が群れをなしてあるだけの神社を拝みある」いています。
1月4日
田名部に滞在しています。暦の上では4日ですが、3日ということになります。節分なので豆まきをしています。
1月6日
田名部に滞在しています。今日は5日ということになります。屋内の柱の上方に松をたて、柱のもとには鱈や鮭を供え物として積んであります。高い窓から吹きこんできた雪が魚の上につもっています。
1月8日
田名部に滞在しています。今日は7日ということになります。七草の粥を食べます。七草がないので塩漬けの「たかな」などをいれます。
1月9日
田名部に滞在しています。とりの日だというので、三寸ほどの紙に「酉」と書いて門の戸にさかさまに貼っています。
1月11日
田名部に滞在しています。大畑では船だまの祝のある日です。田名部では今年はじめての市日です。
人ごとに小さな「かれいげ(弁当箱)」を持ち歩いています。この日、塩、針、飴の三品を買う習慣があるからです。
民間では今朝から暦のとおりの日に戻ります。武家では二十日のめだしの祝から普通の暦に戻ります。
1月13日
田名部に滞在しています。目名(東通村)の優婆塞(山伏)たちが三年に一度の獅子舞という神楽をして門ごとに巡っています。この獅子舞が和歌山某の新築した家にきて舞い歌いながらお祓いをします。終わってごちそうすると酔って帰っていきます。
1月14日
田名部に滞在しています。昨日ついた餅を、粟穂、まゆ玉としてみずきの枝や柳の枝につけています。
夕暮れ近く、子供たちが田をうつさまを人形に作ったものを持って、門ごとに「春のはじめに『かせぎどり』まゐりた」と呼ぶと「どちらの方から」と問い、「あきの方から」と答えます。
夜がふけてから、魚のひれとか皮などを餅とともに焼串のようなものにはさんで家々の戸ごとにさして歩いています。
1月15日
田名部に滞在しています。男の子は菅原道真公の像を家の隅にまつり、女の子はひな祭りをしています。松前とだいたい似ていると書いています。
昼ころに、湯帷子を着て紅の裾をたかくからげ、はばきをつけ、わらじを履いた田植え姿の女たちが、「えもとさえもがほうたんだ、一ぽん植えれば千本になる、かいとのわせのたねとかや、ほいほい」と鳴子を鳴らしながら歌い去っていきます。
1月16日
田名部に滞在しています。白粥を食べる日です。田植え女が多く群れ歩いています。
1月20日
田名部に滞在しています。めだしの祝が代官のもとで行われる日です。「めだし」とは賽を投げてその目を数えて多さを競うことです。
まゆ玉の餅をおろしていただく日です。
2月1日
田名部に滞在しています。正月のようにこの日も「としとり」をします。厄年の男女がその災の年をすでに過ごしたことにするのです。
2月2日
檜の山を見に主人をはじめ数人をさそって出立します。栗山村から入り、雪が深かったので夕方ころ恐山菩提寺(恐山)に着きます。
2月3日
夜が明けていくころ、案内人の案内で、かんじきを履いて氷結した宇曽利山湖を歩きます。湖の真ん中で木こりたちが出迎えてくれます。
大ぜいの木こりたちが、長さ一丈、二丈の檜の材木を引き出すための雪の坂道づくりをしています。
材木を引き出すようすは、そりに材木を六十本あまり、米七十俵の重さのものを男ひとりの力で引き下ろしていきます。そりの速さは鳥が飛ぶようです。材木を引く者は一人が一日に米二升近く食べますが「世の中にくらべようもない力仕事をするためで、さもあろうと思われた。」と書いています。
与一郎けどという木こり小屋に泊まります。荒くれ男が飯をたき料理してくれます。寒さのきびしい山中ながら絶え間なく火を焚いてくれたので暖かく休みます。
2月4日
山の神に供え物を奉るのに拍子木をうっています。
きつ(木櫃)に飯を入れて細い杵でついて餅にして、これを火の中にくべて焼いたものを昼食にと出してくれます。「たんぱやき」といいます。今の「きりたんぽ」です。
山を降りて山麓の中新田を通り、城が沢に出ます。宇田、川守、安渡、大平を経て田名部に戻ります。
2月11日
田名部に滞在しています。雁をみて、わが父母の国(三河)から来たのではないかと思い、故郷が恋しくなります。
2月16日
田名部に滞在しています。旅から帰って父母に会う夢をみます。
2月23日
田名部に滞在しています。酒屋でいっぱいやってよろけながら帰っていく男たちをみます。
3月3日
田名部に滞在しています。「ああ、いやな雨だ、なな潮も降るだろう」と語り合って行く人がいます。今日雨が降ると潮の満干がいつもと違うことがあるとしてきらう習俗があるからです。
3月4日
万人堂に行って万人帳を見ます。今の時代にはない奇妙な名前をみて、百年以上むかしの世をしのびます。
3月15日
びっつけという浜に行きます。美付といい、むつ市関根の近くです。
3月16日
大畑に滞在しています。今日は農神の祭です。神明社に詣でて帰ってきた人が、農神は去年の十二月に去ってゆかれて今日帰ってくるので耕作をはじめようと言っています。
3月23日
恐山の湯(恐山)に土田直躬を訪ねます。古道川を渡り、田中の観音堂、銅金(どうきん)という山道を行きます。外山村、小高森、大高森、材木沢、井戸桁、上小河山、谷地山、剣山を経て恐山に着きます。
3月24日
恐山に滞在しています。湖の岸辺をしばらく散歩します。
3月25日
恐山に滞在しています。まだ暗いうちからうぐいすがさえずっています。
目次のページ>青森県の歴史の目次>菅江真澄が歩いた青森県>このページ